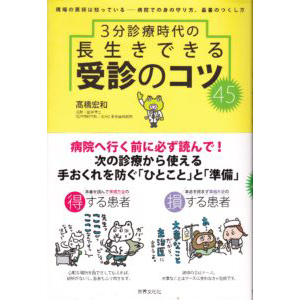症状に関するQ&A
Q.家族の物忘れがひどいのですが病院に行きたくないと言います。どうしたらよいですか?
A.物忘れの場合、ご本人も内心心配しつつ認知症の可能性を認めたくないという心理も働くようです。
「万が一なにか脳の病気があったら大変だから念のため病院で診てもらいましょう。なにもなければ安心だし」とやんわりと受診を促すのがおすすめです。
どうしても本人が病院に行きたがらない場合には、まずはご家族だけでも病院や地域包括支援センターで相談に乗ってもらい、状況を整理し、情報収集を始めるのがよいと思います。
Q.物忘れと認知症との違いは。
A.物忘れと認知症の違いは「同年代と比べて忘れっぽさが目立つ」「日常生活に支障がある」です。
記憶力や判断力など、今まで身に着けてきた能力が徐々に衰えてゆくことを認知症といいます。アルツハイマー型認知症以外にもたくさんの病気が認知症の原因となります。
例えば低血糖や電解質異常、甲状腺機能低下症やビタミンB12欠乏症などは血液検査で発見できます。特発性正常圧水頭症や慢性硬膜下血腫もCTなどで発見できます。薬の副作用でぼーっとなることもあります。
原因を調べ正しい治療をすることが大切です。
Q.認知症の早期発見の目的は。
A認知症には様々な原因があります。
早期発見することにより迅速に適切な治療ができます。
一番多いアルツハイマー型認知症の場合、薬物治療で症状改善やある程度進行を遅らせることができます。
認知症と診断されることは心の負担になる可能性がありますが、認知症であることを前提にライフプランの見直しや、薬物治療以外にも必要に応じた介護サービスの導入をすることができます。
Q.家族が最近急に怒りっぽくなりました。認知症でしょうか。
A.65歳以上の高齢者の約15%が認知症といわれており、珍しい病気ではありません。
認知症の中でも脳血管性認知症では気力や意欲の低下、逆に感情のコントロールがしづらくなることもあります。前頭側頭型認知症でも怒りやすくなることもあります。診察や画像検査などで診断していきます。
急に怒りっぽくなる場合、認知症以外の原因もチェックします。認知症の薬の一部で怒りっぽくなることがあるため、薬の確認も必要です。その他、脳の病気やホルモンの病気などで急に怒りっぽくなることもあり得ます。正確な診断に基づく治療が必要です。
Q. 母が時々ぼーっとして視点が定まらなくなったり、話しかけても反応がなくなります。
A.時折ぼーっとして会話が成り立たなくなる場合、「非けいれん性てんかん」かもしれません。短時間、意識や記憶が途切れたりすることを繰り返すのが「非けいれん性てんかん」の特徴です。
認知症でも忘れっぽさが目立ちますが、「非けいれん性てんかん」の場合には普段は忘れっぽさなどは目立たずふつうにしていることが違いです。
認知症と「非けいれん性てんかん」では治療法も違うので、正しい診断が重要です。
Q.手のふるえが気になります。
A.手のふるえを起こす病気にはパーキンソン病や本態性振戦や甲状腺機能亢進症など様々な病気があります。病気によって症状の進み具合も治療法も違います。
いずれの場合も、原因を調べ適切な治療をすることで症状は軽くなります。
Q.夜寝ようとすると脚がむずむずして眠れません。
A.「むずむず脚症候群」かもしれません。
夕方や夜に起こる脚の不快感・むずむず感と脚を動かしたくてたまらなくなるという欲求が症状です。
原因不明のことが多いですが、鉄分の欠乏が原因のこともあり血液検査で調べます。
原因に合った薬で症状は改善します。
Q. 頭痛があり、頭痛薬を内服しています。
A.いろいろな種類の頭痛があります。
緊張型頭痛はしめつけられるような鈍くて持続的な頭痛です。頭痛薬が比較的よく効きます。片頭痛や群発頭痛では市販薬はあまり効きません。
片頭痛では、ずきんずきんと脈を打つような強い痛みが起こり、吐き気を伴うこともあります。動くと痛みが強まるので、片頭痛の発作のときにはできるだけじっとして痛みが治まるのを待つ人が多いです。
群発頭痛は男性に多く、夜間などに目を刺されるような痛みがしばらくの期間、毎日おそってきます。
頭痛薬を連日飲むような状況では、薬物乱用頭痛も心配です。
それぞれの頭痛は、適切な治療でよくなります。
Q.ときどき目の前がチカチカして視界が欠け、しばらくすると強い頭痛が襲ってきて吐き気もします。
A.
片頭痛の前兆として目の前にチカチカとした光が見えることがあります。
「閃輝暗点(せんきあんてん)」と呼ばれる症状で、視野の一部が欠けることもあります。片頭痛の症状は出ず、閃輝暗点の症状だけ出ることもあります。
典型的な片頭痛ではズキンズキンと脈打つように頭が痛くなり、吐き気を伴います。音や光、においに過敏になり、動くと響くため薄暗い部屋で静かにじっとしてやりすごすしかない人もいます。
片頭痛そのものは命の危険を伴いませんが、片頭痛以外の病気のチェックをしておくと安心です。
片頭痛は市販の頭痛薬が効かないことが多いですが、病院で処方される薬は比較的よく効きます。片頭痛の治療は進歩しており、症状緩和だけでなく、片頭痛の予防のためにもさまざまなお薬が使えるようになってきました。適切な治療により苦痛は軽くなります。
Q.最近、階段の昇り降りなどがしんどく、うまくいきません。なにか悪い病気でしょうか?
A.まず大事なのは症状がどれくらい急に進んだかです。何年もかけて悪くなった場合、加齢などの可能性があります。
診察では、特定の筋肉だけ力が弱くなったのか、全体に筋力が落ちているのかをチェックします。また、感覚の鈍さやしびれ感などがあるか、腱反射はどうか、血液検査などを組み合わせて診断を進めていきます。
よくつまずく場合、つま先を持ち上げる筋肉などの働きが弱っている可能性があり、末梢神経の病気を疑います。
下りよりも昇りが大変な場合は、近位筋というふとももなどの筋力の問題かもしれません。その場合には筋炎やリウマチ性多発筋痛症など筋肉の病気を疑います。
脳の病気では左右どちらかの症状が目立つことが多いため、そこもポイントです。
その他、ひどい貧血や肺、心臓の病気などでも息切れがしたりして階段昇降が億劫になることがあります。
Q.うまくしゃべれないときがあります。
A.自覚的にはうまくしゃべれなくても、まわりから指摘されることが無ければ気にしすぎかもしれません。一方で、まわりから指摘されたり、電話相手によく聞き返されていたら要注意です。
うまくしゃべれない、話せないとき、思っているイメージを言葉に変換できない、適切な言葉を探せない場合と、言葉をうまく発音できない場合があります。
イメージがうまく言葉に変換できない、適切な言葉を探せない場合は、言語に関する脳の部分の病気の可能性があります。診察や頭部CT、MRIなどを組み合わせて診断します。
うまく発音できない場合、「るりもはりも照らせば光る」や「パタカ」という言葉を繰り返してスムーズに発音できるかなどを診ます。「パ」という音は唇、「タ」は舌、「カ」はのどを使います。それぞれの機能を調べながら、声の大きさやスムーズさ、リズムも診ていきます。